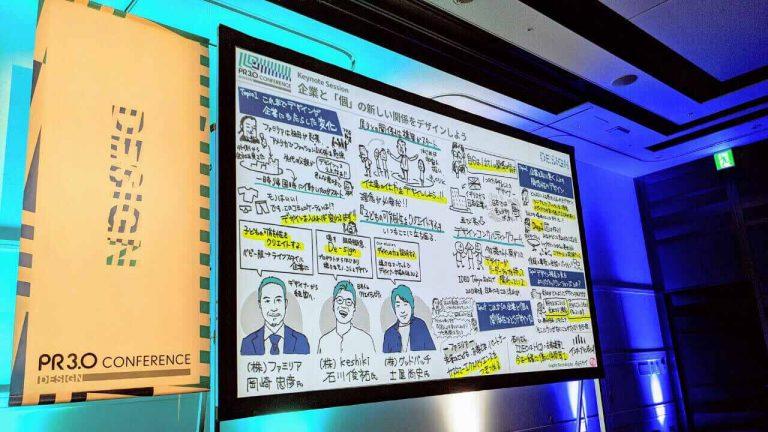メディアのあり方や未来について考えるメディア従事者向けの祭典「MEDIA DAY TOKYO 2023」が、2023年7月20日に開催されました。今回のイベントは、株式会社PR TIMESが主催・企画を担い、CINRA,Inc.が企画・運営を務めます。2018年以来、5年ぶりに開催され、業界の最前線で活躍する多数のメディア関係者が集結。登壇者の熱いトークセッションを聞き、会場は盛り上がりました。
「DXが進んでも成長する紙メディアの仕掛けとは?」をテーマに、株式会社晋遊舎取締役編集局次長の木村大介さん、神戸新聞社DX推進局次長・ジェッソ取締役の藤原学さん、株式会社宝島社執行役員第2雑誌局局長兼『リンネル』編集長の西山千香子さんを迎え、PR TIMES高田の進行のもと、展開されたトークセッションの内容をお届けします。

株式会社晋遊舎 取締役 編集局次長/セールス&マーケティング局長
1978年東京都生まれ。生活情報紙記者、広告・広報制作を経て、2010年に株式会社晋遊舎入社。2016年にLDK編集長就任後、2017年に『LDK the Beauty』を創刊し編集長を兼任。現在は編集の現場を離れ、テストメディアの新たなマネタイズを模索する新規事業を中心に活動。

神戸新聞社DX推進局次長 ジェッソ取締役
1993年神戸新聞入社。社会部(現・報道部)記者&デスクとして22年間活動。ほかに阪神総局、姫路支社で勤務。主に事件(神戸連続児童殺傷事件、JR尼崎脱線事故、尼崎連続変死事件など)や選挙、行政取材を担当。販売局企画開発部長などを経て、2020年にDX推進部長、2023年から現職。

株式会社宝島社 執行役員 第2雑誌局局長 兼 『リンネル』編集長
1969年兵庫県生まれ。2000年宝島社入社。2010年『リンネル』の月刊化と同時に編集長に就任。2014年には40〜50代をターゲットにした『大人のおしゃれ手帖』を創刊し、2誌の編集長を兼任。現在は、『リンネル』編集長のほか、『大人のおしゃれ手帖』『steady.』の編集部を束ねる第2雑誌局・局長も兼任。

株式会社PR TIMES パートナービスネス開発室長
早稲田大学卒業後、読売新聞東京本社入社。静岡支局を経て、本社世論調査部・編成部の後、政治部。途中、福島支局で復興政策・県庁取材も担当。経営企画部門を最後に退社。大手SNS企業で政府・自治体渉外を経て、2021年1月PR TIMES入社。全国の新聞社や雑誌を含むメディア、金融機関、公的機関等との提携・協業を推進。2022年4月より現職。
プロフィールはプレスリリースより:メディアの未来を考える1日『MEDIA DAY TOKYO 2023』7月20日開催 「エルピス」佐野亜裕美P、「SPY×FAMILY」編集・林士平氏ら登壇!
成長を続ける紙メディアの取り組み
デジタル化が進み、市場縮小の苦境に立たされている紙メディア。しかし、その中でさまざまな新しいアプローチによって追い風をつかもうとするメディアがあります。SESSION4のスタートは、紙メディアが成長を続けるために何ができるのかについてお話いただきました。
付録雑誌のパイオニアが創出する価値
高田さん(以下、敬称略):宝島社はファッション誌のシェアが13年連続1位と、雑誌・出版業界をリードし続けていますが、成長を続けるためにどのような取り組みをされていますか。
西山さん(以下、敬称略):私たちの雑誌の特徴は付録です。もともとは読者との出会いを広げるためのアイテムでしたが、デジタルに置き換えられないコンテンツとしての位置づけに変わってきています。付録は実際に手に取ってもらい、それに対価を払ってもらう、デジタルに変えられないものだと思います。
とはいえ、20年も続けていると読者は斬新さや驚きも感じなくなってしまうため、私たちなりに3つのチャレンジを重ねてきました。
1つ目はコラボアイテムの新規開拓。アパレルブランドとのコラボレーションのほかに、ムーミンやスヌーピー、ミッフィーなどのキャラクターとコラボすることがひとつのトレンドになっています。また、企業とコラボ付録を作ることも始まっていますね。
2つ目は新たなアイテムの開発です。これまでの付録はバッグやポーチが主流でしたが、最近はハンディーファンやガラスの耐熱容器など、10年前には付録につくことが想像もされなかったようなものを、いかに安価で作るかにチャレンジしています。
そして、3つ目は流通です。各コンビニチェーンと提携して、そのコンビニの限定付録を提供する取り組みをしています。
同じようなものを付録にすると明らかに読者からの反応が悪くなるため、常に読者が見たことがない新しいものを作っていくことを、原価や流通のルールと戦いながら頑張っています。
中立な立場を徹底し生活者が求める情報を提供
高田:雑誌『LDK』は、「テストする女性誌」として生活に関する商品を取り上げている雑誌ですが、「テスト誌」を始めようと思ったきっかけや、その結果についてお聞きしたいです。
木村さん(以下、敬称略):家電雑誌やモノ雑誌のジャンルで地位を確立している他社の雑誌がすでにある中で、われわれが勝つためにどうすればよいか、モノ選びの生活者の不満を解決するためにどうしたらよいか。それらを考えたことがひとつのきっかけです。
モノ批評雑誌『MONOQLO(モノクロ)』の創刊は今から16、7年前。当時は広告収入と実売の2本柱で収益を上げるのが出版業界の常識でした。しかし、広告収入を一切得ずに、あらゆる商品に対するテスト、格付けを世に発信したところ、すごく反響が大きかったんです。男性向けの生活情報誌だったのですが、女性の読者も多く、女性向けコンテンツもやってほしいという要望に応えて『LDK』をスタートしました。
『LDK』の特集で何ヵ月かに1回、コスメのテストを取り上げていたのですが、毎回大変な反響だったため、コスメをテストする専門誌『LDK the Beauty』を創刊しました。当初は編集部員と外部の検証機関が一緒に行っていた商品のテストも、現在は予算をかけて社内にラボを作り、検証機関から専門スタッフに入社してもらい運営しています。
読者の期待に応えるため、メーカーが一生懸命開発した商品に対して、しっかりした検証で対応をするべきという考えから、ラボにコストをかけて検証の質を上げていきました。
高田:新しい挑戦を企業としっかり手を組まれている部分と、よい意味で企業と距離を置いて中立的な立場でやっているという印象があります。
木村:「メーカーからクレームは来ないのか」とよく聞かれますが、間違いに対する指摘をいただくことはあっても、それほど大きなクレームはないんですよ。
メーカーの方と話していて感じるのは、メーカーも欠点は理解しているということ。われわれのような第三者評価を口実に社内で予算を投じやすくなったり、リニューアルや改良に成功したりしているケースもあるそうです。また、メーカーも読者が雑誌を見て商品を選ぶことに慣れてきています。どうすればよい評価につながるのか、ひとりよがりの商品開発ではなく、マーケットインを重視するようになってきているのかなと思います。
地域に出て積極的なプロモーションを展開
高田:神戸新聞では、2022年4月から東京都在住の小説家・早見和真さんと愛媛県出身の絵本作家・かのうかりんさんによる創作童話『かなしきデブ猫ちゃん』の連載が始まり、大きな反響がありました。その取り組みについて詳しく教えていただけますか。
藤原さん(以下、敬称略):新聞はスマホが登場して以来、人口減少のように打ち手がない状態が続いています。きちんと届ける努力「プロモーション」をしているのだろうか。読者に対する付加価値体験を与えられていないのではないか。生き残っていくにはどうしたらいいのかをすごく考えました。
そして、アナログも含めて展開してみようと始めたのが『かなしきデブ猫ちゃん』でした。『かなしきデブ猫ちゃん』はもともと愛媛新聞が2018年に始めた連載。毎週同じ曜日に週刊性を持って掲載するコンテンツがどうしても必要だと感じていたときに出会った作品で、2021年4月から第1シーズン、2023年4月から第2シーズンが始まりました。
今までの新聞社は、自分たちの「おもしろい」の価値観を基準にしてやってきてしまった。もちろん、ジャーナリズムを担ううえで必要ですが、おもしろいコンテンツを作るためには、読者の「おもしろい」の価値観を無視してはいけません。
また、プロモーションが大切だということを痛感し、さまざまな取り組みを行いましたね。
- 特設ページの開設
- 県内57,000人の小中学生へ電子版新聞「まなびープラス」で全話無料公開
- X(旧Twitter)、Facebook、Instagram、TikTokなどのSNSを開設
- ポスター、フライヤー、クリアファイル、16種類の名刺などアナログツールの展開
- 自治体を中心としたイベント会場への参加
- イベントやワークショップの開催
- 学校や地元企業とのタイアップ
- 絵本の販売(発売2週間で4,000部を突破、重版決定)
2年ほど繰り返したこのような取り組みは、読者からの反響も大きく、生活者の行動変容につながった手応えを感じるものでした。

紙メディアが挑む変革
長い歴史の中で培ってきた黄金のビジネスモデルを持つ紙メディア。デジタル化の加速によって変革を求められる今、過去の成功体験が足かせとなってしまうケースもあります。その中で紙メディアはどのように新しいチャレンジをしていくことができるのか、それぞれの取り組みを伺いました。
雑誌の垣根を超えた革新的キャンペーンを
西山:宝島社が昨年から取り組んでいるプロジェクトのひとつに「Hello Femtech」があります。フェムテックは、コロナ禍で非常に盛り上がったテーマですが、男性誌も含む全誌を挙げて取り組んでいるところです。
これまでは同じ会社の中でも、雑誌ごとの考えが強く、雑誌を跨いだ取り組みはなかなかできていませんでした。しかし、私たちは広い世代の読者を持っている会社。せっかくなので、雑誌の枠を超えてこのテーマに取り組んではどうかと思ったのです。
さまざまなイベントや雑誌を横断した企画を行い、少しでもたくさんの人に知っていただく。それぞれの雑誌の読者にしか届けられなかった媒体のよさを、ほかの雑誌の読者にも知っていただく、機会になっていると思います。
高田:キャンペーンは収益に結びつかないことが多いですが、なぜやろうと思ったのでしょうか。
西山:PRすることや存在感を高めていく必要性を感じていたんです。私たちの雑誌は、過去にテレビCMをしていたこともありますが、そのコストを事業に振り分けて何かを生み出す・生産することに投下していきたいと思っていました。その中で、自分たちができる効果的なPRを考えた結果、雑誌を跨ぎ、キャンペーンを大規模にしていくことになり、社内的にも大きな推進力となっていると感じてます。
ブランド力を高め新規事業の創出につなげる
木村:よく紙メディアが衰退している理由に、Webやスマホの台頭が挙げられますよね。確かにそれが直接的な理由なのは厳然たる事実ですが、実際にわれわれの媒体は初期のころから電子書籍へシフトしたり、オウンドメディアで情報を出したり、SNSを使った発信をしていました。当然、本を売る部署からの反発や制限をかけるような動きはありましたが、コンテンツに関していえば、いずれWebに移行していくだろうということは、私自身は当初から想像していたんです。
今実際にそういう時代になって思うのは、紙が持つ権威性や信頼感、お金や時間をかけてコンテンツを作れる環境を加味すると、Webコンテンツと余裕で戦っていけるということ。例えば晋遊舎の媒体が20万部ある中で、それが電子化し、Webの台頭で10万部発行部数が減ってしまったとしても、10万人のリーチが減ったわけではありません。電子書籍で読んでくださる方が増えたり、30数万人いる『LDK the Beauty』のInstagramのフォロワーが読者になってくださったり、他社のプラットフォームに情報を載せていくことでコンテンツのタッチポイントはかなり増えています。その証拠に、部数は落ちているけれど、雑誌に取り上げた商品のPOS(Point Of Sales)が明らかに動くんです。
メーカー側からはベストだった商品の「ベストバイマーク」を使う権利を譲ってほしいという声もあり、メニュー化しました。広告や実売でお金を取るという紙メディアの従来のビジネスモデルから脱却し、紙をひとつの象徴としてビジネスを創出していく。紙メディアの持つブランド力によって既存しないビジネスをいっぱい作っていく。そうすることで出版が波に乗っていた時期よりも最高収益を出すことができているんです。
予算の問題解決のために社内ベンチャー設立
藤原:会社の組織は、取締役会の下にさまざまな局がぶら下がって縦割りになっていますが、それでは物事がなかなか進みません。そこでわれわれのDX推進局は取締役会を取っ払って、社長直轄の組織にし、とても動きやすくなりましたが、予算の問題は残っていました。
予算は年初に決められており、年度途中で起案された新しい事業は追加稟議が通らない限り実施できません。そうした問題を解決するために、社員と友好会社で社内ベンチャー「Gesso(ジェッソ)」を作りました。
主な事業は、神戸新聞の中で伝えたコンテンツを深堀して配信する読者参加型の動画のお祭り「神戸新聞フェス」、ハイパーローカルな動画チャンネルを届ける「KOBE_TV」など。ライブスタジオも神戸新聞の10階に作り、記者サロンの開催やライブ中継を通して読者とつながっていく仕組みにしました。先ほど木村さんがおっしゃったように、メディアの信頼性を基本にいろいろな事業をぶら下げていくことが非常に大事だと思います。
紙メディアのこれからのマネタイズ
高田:メディアにとっての大きな問題のひとつに収益減があると思います。これについてはどのようにお考えでしょうか。
木村:紙メディアやオールドメディアといわれている業界はとにかく編集者が強いんです。でもその人たちはお金を稼ぐという意識が弱いと個人的に感じています。出版業界は新規参入しにくいところがあり、Webが浸透していないころはコンテンツも限られていたため、稼ぐことを意識しなくてもやっていけていました。今でもそういう部分があり、その点への危機意識は強いのではないでしょうか。
もちろんよいコンテンツを作る意識は大事ですが、それを使ってどう稼ぐか、もしくは、稼ぐことを真剣に考える人にどう協力するか。そこを自分ごととして考え、マネタイズする努力ができれば、紙メディアのブランド力や信頼性はすごく高くなるはずです。
われわれの場合は、テストメディアという強みを持っていて、コストや時間をたくさんかけているわけですから、読者に向けて発信しつつ、健全にメーカーさんに活用していただくルートを作りました。出版業界の編集と営業がお互いを理解し、一体となって目的に向かっていくことができればすごく強いと思います。編集のポリシーや営業のミッションを相互理解することで戦い方が変わる、とここ数年感じています。
ポテンシャルが高いうちに種を蒔く
高田:メディアでは昔から編集と経営は分離するべきだといわれていて、営業の依頼に応えることや稼ぐことへのこだわりを持つことはよくないと本能的に感じる部分があります。ですが営業と編集の対話、二項対立を克服した先には可能性があるのかなと思いました。
藤原:神戸新聞は500人いる社員のうち300人ぐらいが編集記者です。つまり200人で神戸新聞の収益を稼ぐことになります。普通であれば人件費も含んだ事業で赤字・黒字を出しますが、新聞が売れていたときは、その点を考えなくてもやれていたんです。ところが最近は、新聞広告と発行部数の減少というダブル苦境の中で編集記者がコンテンツを作り、利益も出していかなければなりません。
新聞社の経営は盤石ではなく、命運をかけた新しい取り組みが必要です。デジタル時代で新しい事業がやりやすくなっているので、紙の持つ強さや信頼性、知名度が浸透している間にそういうものを作っていく。雑誌社や新聞社が持つポテンシャルがまだ高いうちに種まきをして、数年後に刈り取れる事業を仕込んでいくべきでしょう。
知見を生かした新たなビジネスモデル
西山:今後雑誌がどのようにして収益をあげていくのかは、私たちも日々頭を悩ましている部分ですが、『リンネル』では結構な収益を上げている取り組みもあります。
3年ほど前、全国1,000店舗ある衣料品チェーンの「ファッションセンターしまむら」と、当社のもうひとつの雑誌『In Red』と協業ブランドを立ち上げました。商品の販売はしまむらさんの売り場で行いますが、洋服やタグのデザイン、販売プロモーション戦略を一緒に考えることでロイヤリティをいただくビジネス展開で、これが金額的にも今とても大きな支えとなっています。
もうひとつの取り組みは、『リンネル』と住宅メーカーがタイアップして、建売住宅のシリーズを作らせていただきました。私たちは住宅の仕様やデザイン、プロモーション戦略を考え、住宅メーカーが全国の工務店さんに卸し、工務店さんがお客様に販売します。1棟売れたらリンネルに何%か入るという契約です。
私たちが持っているライフスタイルへの知見をどのようにお金にしていくのか。実はそれを求めてくださる企業はまだまだたくさんあって、私たちはその知見を世に送り出せるように日々編集力を高めていかなくてはなりません。これまではタイアップ費用として企業から一定額を払われるケースが多かったのですが、そこからもう一歩踏み出し、協業という形で労力や知恵をお互いの収益につなげていくかが今後の生き方かなと思います。

デジタルが進む中での紙メディアの成長
活発なディスカッションが交わされる中、セッションはいよいよ終盤へ。デジタル化が加速する現代で紙メディアはどのように成長していくことができるのか、熱い思いが語られました。
西山:デジタルの登場で表現の出口が広がったことは、可能性が広がったという意味でありがたい話です。一方で、限られたヒューマンリソースや予算をどのように媒体に振り分けていくのかは、みなさんが本当に悩んでいる問題だと思います。将来に向けての種まきをしたいと思いながらも、巻いてくれる人の数はどんどん減っていますし、土地だけが増えているイメージです。
でも、ここにいる3人が共通して思っていることは「紙メディアが作るコンテンツやブランドの信頼性やブランド力はまだまだ生きている」ということ。増え続ける媒体の中で、いかに効率的にどのようにクオリティを保ちながら新しいものを作っていくのか、みなさんの知恵をいただきつつ、ぜひまたいつかどこかの機会に話し合いたいと思います。
木村:毎年わずかながら新卒採用をしていますが、今年は「本は買ったことないけどインスタで知ってます」という人がついに入社しました。そういう時代になったのだと実感します。5、6年前なら、うちの本を読んだこともない人を採用するわけがないという感じでしたが、Webで知ってくれているなら全然いいかと。また、反対にこれはチャンスだとも思っていて、そういう層が増えている中で、どのようにしてその人たちに刺さっていくのか、そこを考えた戦い方をしていけばいいわけです。
私はWebやSNSを敵視していないどころか、感謝しています。協業させていただいている多くのプラットフォームをさらに広げていきたいですし、既存メディアともご一緒できるようなミッションやテーマがあればぜひ挑戦してみたいと思います。
藤原:「デジタルが進めば紙がなくなる」という仮説があるんですが、私の中では本当にそうなのかという思いが常にあるんです。きちんとコンテンツを作り、そのプロモーションをデジタルで出していけば、むしろより紙の長寿化になると、『かなしきデブ猫ちゃん』の経験から実感しています。紙であってもデジタルであっても、「届ける工夫」を私たちはしっかりやっていく。学びや気づきを得て、きちんとCDPAサイクル(Consciousness、Decision、Preparation、Action)に落とし込みながら力にしていくことこそ、今後の紙の可能性にもつながりますし、デジタルが台頭する中でひとつ頭を出して牽引する力になっていくのではないでしょうか。

DX時代にも褪せない紙メディアの魅力
急速にデジタル化が進むメディア業界。紙が持つ手触り感はこのまま失われてしまうのではというほど紙メディア市場は小さくなっていますが、長年蓄積された紙メディアの権威性や信頼性、ブランド力は、強みにもなることがわかりました。
デジタルを敵視せず、賢く活用しながら新たなチャンスにつなげていく。変化を恐れずにこれまでのビジネスモデルから一歩踏み出し、新たなチャレンジに取り組む。紙メディア業界に携わる一人ひとりにとって、紙メディア業界と一緒に仕事を進める広報PR担当者にとって、多くのヒントが詰まったセッションとなったのではないでしょうか。
【関連記事】
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする