広報・PR活動において、企業や業界、製品・サービスに関する基本情報をわかりやすく整理し、メディア関係者や外部パートナーに理解を深めてもらうための資料が「ファクトブック(ファクトシート)」です。信頼性のあるデータや背景情報を一元化することで、取材対応の効率化や情報発信の精度向上にもつながります。
本記事では、ファクトブックを作成する目的や活用メリットをはじめ、記載すべき基本項目や、作成時に押さえておきたいポイントを詳しく解説します。初めて作成を検討している広報・PR担当者の方はもちろん、既存資料の見直しを考えている方にも役立つ内容です。ぜひ参考にしてください。
ファクトブック(ファクトシート)とは?
ファクトブック(ファクトシート)とは、企業の事業内容や ミッション、歴史、業績などの基本情報や、業界全体および製品・サービスに関する情報を事実に基づいてコンパクトにまとめた資料のことです。
社内外のステークホルダーに「企業の全体像」を短時間で理解してもらうことを目的としており、広報・取材対応・採用・営業など、さまざまな場面で活用されます。
よく混同されがちな資料として「プレスキット」がありますが、プレスキットは主に報道関係者向けに提供されるもので、ロゴ・写真素材・過去の掲載実績など、視覚的・メディア対応に特化した情報が中心です。一方、ファクトブックは「定量データ」「社会課題との接点」「業界における自社の立ち位置」など、より構造的・背景的な情報が充実している点が特徴です。
ファクトブックを作成する目的・メリット
ファクトブックを作成する目的は、メディア関係者に自社や業界、商品・サービスに関する理解を深めてもらい、取材・報道する価値を見出してもらうことにあります。
自社が取り組んでいる領域の社会課題が根深いほど理解は難しくなるものですが、解決した際の社会的インパクトは大きくなります。ファクトブックは、「自社が取り組んでいるのは非常に重要な課題なのに、その複雑さゆえに理解されず取材・報道されない」と悩んでいる広報PR担当者にとって有効な手段です。
メディア関係者にとっても、複雑な課題に関してデータがわかりやすくまとまっている資料は重宝します。ファクトブックがあることで取材がスムーズに進むというメリットもあります。
その他、採用や営業など多用途での再利用が可能です。
ファクトブックを活用できるシーン
ファクトブックを活用できるシーンとして、メディアや報道関係者向けの「取材対応」「メディアキャラバン」の2つが挙げられます。
広報PR担当者として取材対応を行う際に、細かい数値がパッと出てこないときなどがあるでしょう。そんなとき、ファクトブックが手元にあれば必要な数値をすぐに調べて伝えることができます。
また、メディア関係者が記事を書く際にファクトブックを参照してもらえば、企業や業界のデータを調査する工数が減るため、取材しやすい企業だと認識してもらえるでしょう。
メディアの編集部・制作現場を訪問し、限られた時間で情報提供を行うメディアキャラバンの場面では、自社の情報を手早く、かつ幅広く知ってもらう必要があります。そのときファクトブックを手渡し記者・編集者に直接読んでもらうと手短に情報が伝えられます。さらに、ファクトブックに記載した情報をもとに意図しなかった切り口で取材を検討してもらえる可能性も考えられます。
その他、採用イベントやインターン向け説明資料などとして、また営業資料や協業先との打ち合わせ資料としてなどにも活用できます。
ファクトブックに必要な5つの項目
ファクトブックにはどのような内容を記載するのでしょうか。ここからは、ファクトブックに必ず入れておきたい5つの項目について解説します。
参考:『新版 広報・PRの基本』(山見 博康)
項目1.解決を目指す課題
企業が事業や製品・サービスを通じて解決したい社会課題について記載します。課題に関する理解が深まれば、間接的に事業や製品・サービスの必要性をメディア関係者に伝えることができます。
社会課題は数値を用いてファクトベースで記載します。メディア関係者にとってデータの信頼性は重要になるため、自社調査よりも第三者機関による調査結果があるとベターです。
データを使う際はグラフや表を活用し、見やすくデザインするようにしましょう。
項目2.主力商品の説明と業界におけるポジション
企業の主力事業や主力の商品・サービスについて説明します。項目1で記載した社会課題に対し、自社の事業・商品・サービスがどのように解決に寄与するのかを伝えましょう。業界全体におけるポジションをカオスマップやマトリックスなどの図表で表せるとわかりやすく、メディア関係者にも重宝されます。
他社との差別化ポイント(USP)を説明する際は、宣伝色が強くならないよう客観的な内容にすることを心がけましょう。
項目3.事業や商品別の売上高やシェア、販売数
事業や商品別の売上高、シェア、販売数などのデータを記載します。特に経済系のメディアにとって重要な情報であるほか、そのほかのメディアでも「累計○○個売れている商品」など枕詞として使われる可能性があります。
企業の設立年数にもよりますが、過去5~10年間の業績推移を記載できるとよいでしょう。
また、項目2で紹介した主力事業(主力商品・サービス)以外にはどのような事業・商品・サービスを展開しているのか全体像を明らかにし、売上構成比なども開示します。
項目4.従業員数の推移
従業員も企業の重要な資本(人的資本)です。従業員数の推移やおおよその年齢・男女比などの構成をデータとしてまとめておきます。外部からの表彰を受けた者や博士号取得者がいる場合、そうした情報を公開するのもよいでしょう。
福利厚生や人事評価などについても、独自の取り組みを行っている場合は実績などファクトを中心に記載しておきます。
項目5.歴史や創業の経緯
企業が持つ歴史や創業の経緯などについても簡単に記載します。代表や経営層の経歴などについても説明しておくと、メディア関係者の目を引く可能性があります。
ファクトブックはデータを中心にまとめるのが基本ですが、自社のカラーやカルチャーを伝えるため、この項目ではある程度ストーリー性も意識するとよいでしょう。
ファクトブックの作成手順と担当者がやるべき準備
ファクトブックを初めて作成する際は、何から始めればよいか迷うことも多いものです。そこで次に、広報・PR担当者が実際に取り組むべきステップを4段階に分けて解説します。
用途に応じた情報の選定から社内確認、公開の設計までを丁寧に進めることで、信頼性と再現性のある資料を効率よく完成させることができます。
STEP1.目的の明確化と活用シーンの整理
まずは「なぜファクトブックを作成するのか」という目的を明確にします。取材対応用なのか、営業資料として使いたいのか、採用イベントで配布したいのかによって、構成や内容の優先順位が変わってきます。想定する読者(記者、求職者、取引先など)を設定し、どのような場面で使用するのかを関係部署とすり合わせておくと、その後の作成プロセスがぶれずに進められます。
STEP2.必要な情報・実績の収集と棚卸し
次に行うのが、社内にある情報の洗い出しと整理です。会社概要、売上やシェア、サービスの特徴、顧客属性、沿革など、客観的なデータや過去の発表資料を収集します。
広報部門だけでなく、経営企画部、営業部、開発部などと連携しながら、最新かつ信頼性のある情報を集めましょう。既存の資料や過去のリリースも活用し、重複や矛盾がないかを確認することも重要です。
STEP3.レイアウト・構成テンプレートの設計
収集した情報をもとに、ファクトブックの構成とレイアウトを決めます。どの順序で情報を配置するか、見出しの階層、グラフや図解の挿入位置などをあらかじめ決めておくことで、読みやすく再利用しやすい資料になります。
社内デザイナーや制作担当がいれば協力を依頼し、将来的に更新しやすいテンプレート形式に落とし込んでおくと効果的です。
STEP4.社内チェックフローと公開方法の決定
完成後は、記載内容の正確性や表現の適切さを確認する社内レビューが必要です。経営層や法務、IR担当などの関係者に確認依頼を出し、承認フローを整理しておきましょう。
また、PDF、印刷、Web掲載など、どのような形式で配布・公開するかもこの段階で決定します。
さらに、今後誰が更新を担当するか、更新頻度はどの程度かといった「運用ルール」も併せて設計しておくと、継続的に活用できるファクトブックになります。
ファクトブックを作成するときの3つの実践ポイント
メディア関係者が必要としているファクトブックとは、情報が端的にまとめられていて、短時間で企業の実情や成長性が伝わる資料です。以下の3つのポイントを押さえ、メディア関係者に活用してもらえるファクトブックを作成しましょう。

ポイント1. データの信頼性を担保する
メディアに必要とされるファクトブックを作る1つ目のポイントは、データの信頼性を担保することです。
ファクトやデータを提示する際、メディア関係者がそのまま引用できる信頼性の高いソースを用いるようにします。各省庁が発表しているデータや、調査会社のレポートやコンサルティング会社・シンクタンクのレポートなどが信頼性の高いデータといえるでしょう。
自社が保有するデータについては、数を多く見せるなど都合のよい表現をしたくなりますが、鋭い目を持つメディア関係者には見抜かれてしまう可能性が高いです。誇張せず正しい数を示すようにしましょう。
ポイント2. 自社のアピールではなく、業界の構造やトレンドを伝える
メディアに必要とされるファクトブックを作る2つ目のポイントは、自社のアピールを行うのではなく業界の構造やトレンドにフォーカスすることです。
自社に関する紹介が多すぎると営業資料のように受け取られてしまい、最後まで読み進めてもらえません。自社のことばかりを記載するのではなく、業界を取り巻く現状や構造、同業他社の取り組みなどを伝え、業界の全体像を理解できる内容にすることが重要です。
自社・製品・サービスの魅力を理解してもらうより、「業界全体に詳しい企業にもっと話を聞いてみたい」と思ってもらうことをゴールにしましょう。
ポイント3. ストーリー性を持たせる
メディアに必要とされるファクトブックを作る3つ目のポイントは、ストーリー性です。
ファクトブックは定量的な情報を中心にまとめる資料ですが、ただ事実を網羅するだけでは記憶に残らない可能性もあります。どのような課題に対して何を提供するのか、競合優位性はどこにあり、どのようにユーザーを喜ばせ、どう社会貢献をするのか、今後の展望は何かといったストーリー性があると、メディア関係者の理解が進み、記事・番組での取り上げられ方もイメージしやすくなるでしょう。
ファクトブックの事例
ファクトブックは本来メディア関係者に向けて公開される資料ですが、近年ではさまざまなステークホルダーに自社・業界の理解を深めてもらうため、一般公開している企業も見られます。
ここでは、ファクトブックを一般向けに公開している企業の中から2社の事例を紹介します。
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
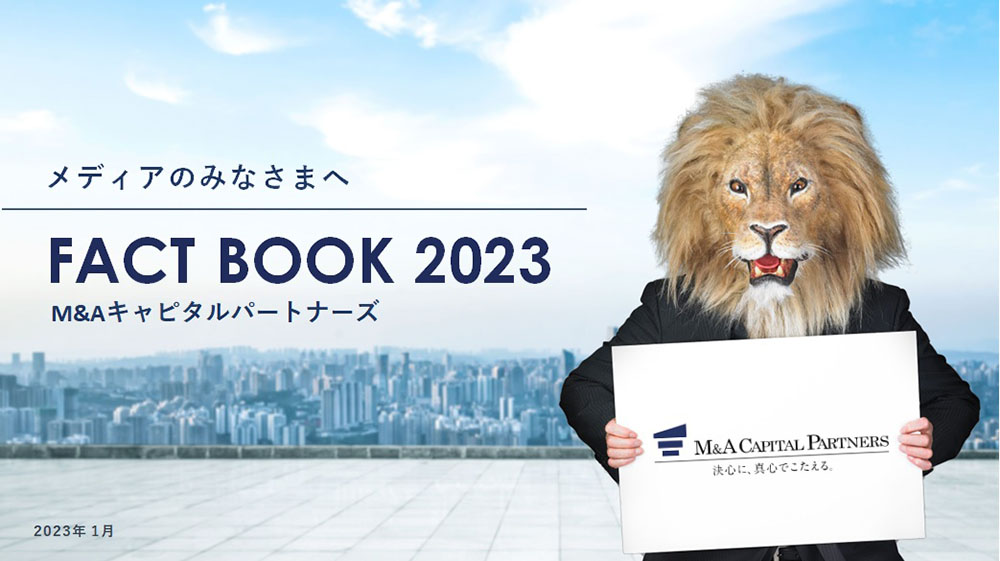
M&A仲介事業を手がけるM&Aキャピタルパートナーズは、M&Aを正確に理解してもらうことを目的にファクトブックを作成・公開しています。
ファクトブックの冒頭で、ファクトブックと決算資料それぞれの目的や違いを説明し、「ファクトブック」という言葉になじみのない読み手にも理解しやすいよう配慮がされています。
前半は経営理念と行動指針からはじまり、会社概要や実積、日本経済への貢献、グループ企業の紹介などがまとめており、後半では、“正しいM&A” をお伝えすることを目的にM&Aを結婚にたとえつつ、その意義や流れ、手法などを解説しています。
データだけでなくイラストを多数盛り込み、「そもそもM&Aとは」という前提知識を提供することにフォーカスしたファクトブックです。
参考:M&Aキャピタルパートナーズ「FACTBOOK 2023」公開のお知らせ
mederi株式会社
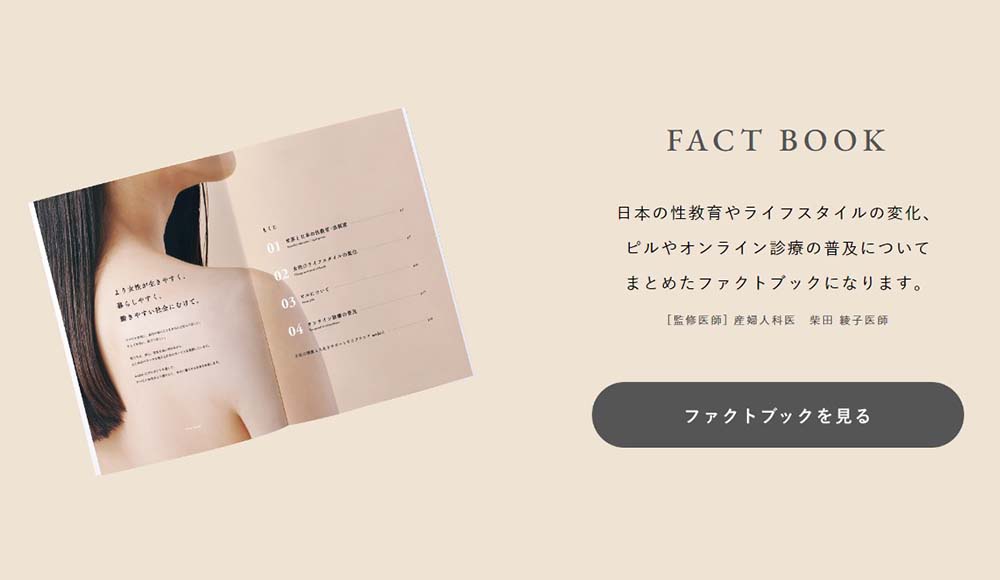
低用量ピルのオンライン診療・処方サービスを運営するmederiは、自社が取り組む社会課題の全体像を伝えることを目的にファクトブックを作成・公開しています。
産婦人科医の監修のもと、世界・日本の性教育や法制度、女性のライフスタイルの変遷、ピルやオンライン診療についてさまざまなデータを紹介。
全28ページのうち、自社の紹介は4ページにとどまっており、自社よりも社会課題について知ってもらうという姿勢を徹底しているファクトブックです。
参考:「メデリピル」リリース1周年を記念しファクトブックを公開!LINE友達登録数は9万人を突破
自社や業界への理解を深めてもらえるファクトブックを活用しよう
ファクトブックは、業界の課題や自社の事業・商品・サービスなどについて、データをわかりやすくまとめてメディア関係者の理解を深めるための資料です。
「自社が取り組んでいるのは非常に重要な課題なのに、その複雑さゆえに理解されず取材・報道されない」と悩んでいる広報PR担当者にとって有効なツールだといえます。
「データの信頼性を担保する」「自社のアピールではなく、業界の構造やトレンドを伝える」「ストーリーを大切にする」という3点に注意し、わかりやすさと自社らしさのそろったファクトブックを作成してみてください。
<編集:PR TIMES MAGAZINE編集部>
ファクトブック(ファクトシート)に関するQ&A
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事
- あわせて読みたい記事広報PR担当者が知っておきたい「ファクトブック」の作り方|5つの基本項目、ポイントと事例を紹介

- 次に読みたい記事オープンファクトブックとは?作成するメリット・流れ・ポイントを解説

- まだ読んでいない方は、こちらから「プレスキット」とは?広報担当者が知っておきたい作り方・必要な7つの項目や事例を紹介

- このシリーズの記事一覧へ

