近年、業界や業種の垣根を越えた企業同士の「コラボレーション」、いわゆる「企業コラボ」が注目を集めています。新たな顧客層へのアプローチやブランド価値の向上など、さまざまなメリットをもたらす取り組みとして、戦略的に活用されるケースが増えています。
とはいえ、いざ自社で企業コラボを企画しようとすると、「どのようなメリットを提示すれば相手企業に協力してもらえるか」「双方の強みを活かすには、まず何から始めればよいのか」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、企業コラボの実例をもとに、その効果や導入時のポイントをわかりやすくご紹介します。
企業コラボをする5つのメリット
はじめに、異なる業界や業種とコラボすることで得られる、具体的なメリットをご紹介します。
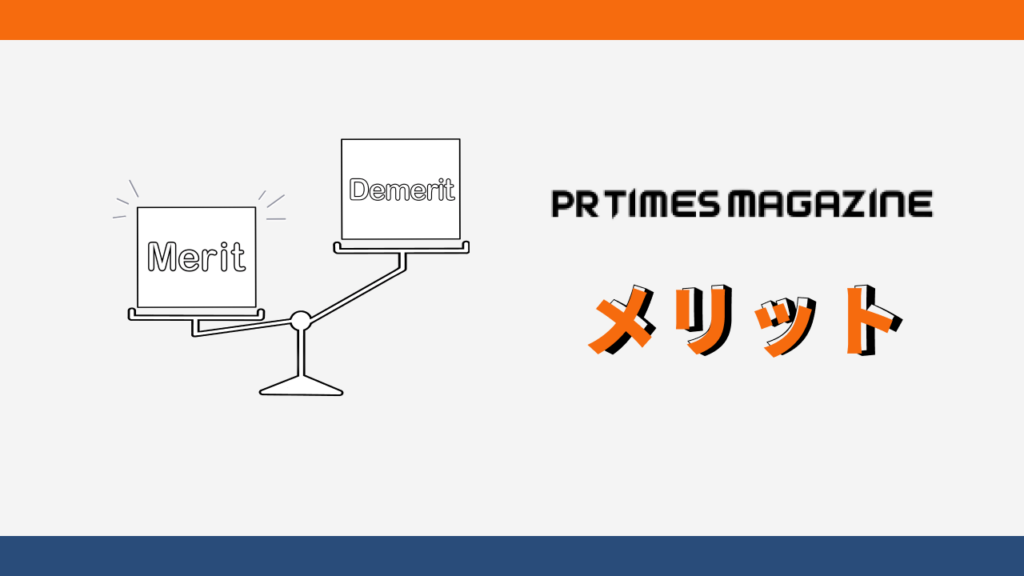
メリット1.認知拡大・新たな顧客層へのリーチ
企業コラボの最大の魅力は、自社単独ではリーチできなかった顧客層にアプローチできる点です。異業種間の連携は意外性がある組み合わせとして話題を呼び、対象者の年齢や趣味趣向の異なる企業同士で組むことで、ファン層同士が交差し、新たな接点が生まれます。
生活者にとって身近な企業や商品がきっかけとなり、これまで関心のなかった分野への興味が芽生えることも。リーチ数の単純な倍増ではなく、異なる質の層を互いに取り込めることが、コラボによって得られる本質的な価値といえるでしょう。
メリット2.話題づくりとメディア発信の促進
異なる業種や世界観を持つ企業同士がタッグを組むことで、報道側にとって取り上げたくなるニュース性が生まれます。互いの広報PRチャネルを活用することで、これまで接点のなかったメディア領域にもアプローチが可能に。
また、コラボのテーマに社会性や時流を意識したストーリー性を持たせることで、報道価値がさらに高まり、SNSでの波及効果も期待できるでしょう。コラボは「ニュース性を自ら設計する」手段のひとつでもあります。
メリット3.ブランドイメージの向上・刷新
企業コラボは、自社ブランドの意味や立ち位置を見直す好機にもなります。これまでアプローチできていなかった層に、新たな共感を得るための一歩として機能します。
広報PRの観点では、自社が伝えたかったメッセージを、相手企業の言葉や世界観を借りて発信できる点もポイントのひとつ。企業の変化や挑戦を、コラボを通じたブランドストーリーとして伝えることで、受け手の受容や解釈も広がります。
メリット4.商品・サービスの付加価値化
コラボから生まれる商品やサービスは、多くの場合「期間限定」「数量限定」「限定仕様」といった希少性を持っています。こうした要素は、商品・サービスそのものの価値を超えた「体験価値」として、生活者の心を動かすきっかけになります。
たとえば、日常使いのアイテムにアートやエンタメの要素を掛け合わせ、話題性とともに、限定性の背景やストーリーを丁寧に伝えることで、「話題になる」だけでなく「選ばれる」理由にもつながるでしょう。SNSでの拡散も見込めるため、広報PR施策としても有効です。
メリット5.共創によるアイデアや技術の融合
企業コラボは、異業種の視点を取り入れることで、思考の枠を超えた新たな発想や表現を生み出します。広報PRや商品開発においても、視野を広げる貴重な経験になります。
さらに、共創による取り組みは中長期的なブランドづくりやマーケティング戦略に好影響をもたらすだけでなく、社内の組織活性化や企業文化の醸成といった「インナーコミュニケーション」の観点でも価値を発揮します。
企業コラボを成功させる3つのポイント
次に、企業コラボを自社で進めていく際に、あらかじめ押さえておきたい重要なポイントを3つご紹介します。
ポイント1.目的について合意形成を図る
まずは、双方の目的を明確にすることから始めましょう。売上拡大、CSRの推進、採用強化など、目的が複数ある場合も、優先順位や共通認識をあらかじめ擦り合わせておくことが重要です。目的が曖昧なまま進めてしまうと、施策や発信内容にブレが生じ、ユーザーへのメッセージもぼやけてしまいます。
SNS投稿やプレスリリースで背景や思いを伝える際も、この「目的軸」があることでメッセージに一貫性が生まれ、共感を得やすくなります。ファン投票や開発ストーリーの公開といった参加型施策を展開する際も、「なぜユーザーを巻き込むのか」という共通理解があることで、コラボの本質が伝わり、単なる話題づくりにとどまらないブランド価値の共創につながります。
ポイント2.社内外の関係者との連携を強化する
コラボ企画は、広報PR部門だけで完結させるのではなく、企画段階から営業、商品開発、法務などの部門も巻き込んだ体制づくりが欠かせません。スケジュール管理や確認フロー、窓口担当の把握など、実行体制もあわせて徹底的に管理しましょう。
社内連携が不十分なままだと、取材対応やプレスリリース配信時に齟齬が生じ、信頼性を損なうリスクが高まります。社外のPR代理店やメディア関係者といったパートナーとも事前に情報を共有し、最適な情報発信のタイミングを調整することで、広報PR効果を最大化できます。
ポイント3.コラボの背景となるストーリーを設計する
コラボでもっとも大切なのは、両者が手を組む背景にあるストーリーです。商品の掛け合わせにとどまらず、社会課題への挑戦や新市場の開拓といったストーリー設計が、メディアに取り上げられるきっかけになります。
異業種コラボの意外性や、日常に新しい選択肢が加わる驚き、共感を得られる社会的意義などを丁寧に描くことで、ユーザーはそのストーリーの一部として自然に参加しやすくなります。発信内容には、ユーザー目線で「体験する意味」を織り込むことが大切です。こうした設計が、生活者に届くメッセージの伝達力と共感力を高めます。
アパレル業界の企業コラボの事例5選
ここからは、個性豊かなアパレル業界の5つのコラボ事例をご紹介します。共通の世界観を軸にした企画や、社会的意義のあるデザインなど、「成功の要因」を具体的に紐解いていきます。

事例1.NIKE×レゴジャパン
- 双方の共通点を踏まえたコラボの目的の明示
- アジャ・ウィルソン選手の起用による話題性の創出
- 関係者のコメントによる企画への信頼性の付与
参考:レゴ®ブロックとのコラボ製品「レゴ® Nike Dunk」2025年5月29日(木)22時予約開始 / 7月1日(火)より一般販売開始
事例2.トチギマーケット×嶋田屋本店
- コラボ背景としての店舗の成り立ちの紹介
- 地酒のコンクール実績をもとにした価値の訴求
- 双方に共通する目的の提示による訴求力の向上
参考:“とちぎの地酒”ブランドほぼ全部を網羅したコラボTシャツ、5月30日より発売開始──栃木県内のほぼ全蔵元の日本酒を試飲できる「嶋田屋酒店宮みらい店」オープン記念!
事例3.アダストリア×エムズ
- ブランドコンセプトに基づくコラボ背景と、新たなサービスの展開を強化
- コラボテーマと対象者層の明確化
- 社会的意義を込めた時勢・需要の反映
参考:「niko and …」がサービスユニフォームの製品を展開している株式会社エムズとのコラボシリーズを開発
事例4.土屋鞄製造所×河合楽器製作所
- プレゼントキャンペーンによる話題性の創出
- 親子向けミニコンサートによる新規層の獲得
参考:土屋鞄のランドセルブランド「grirose」河合楽器製作所とコラボ第2弾 ランドセルカラーの特別仕様『KAWAI meets grirose』ミニグランドピアノ 6月21日(土)より数量限定販売開始
事例5.タカギ×Noblesse Oblige
- 素材・技術力・デザインの融合による商品価値の訴求
- コラボ商品開発の経緯を通したブランド価値の強化
参考:英ランジェリーブランドとコラボ プレミアムインナーウェアAROMATIQUE(アロマティック)が新作コレクションを発表
参考:ロンドン発ランジェリーブランドとAROMATIQUEのコラボ「AROMATIQUE × Noblesse Oblige」第二弾を発売開始
また、同社は他企業とのコラボを通じて、「これまでと異なるデザインの追求によりデザイナーの発想の幅が広がった」ことや、「ブランドの世界観が広がった」ことなど、副次的効果の感じているそうです。
詳細は下記のインタビュー記事をご覧ください。
コスメ・ヘルスケア業界の企業コラボの事例3選
次に、コスメ・ヘルスケア業界の3つの事例を取り上げ、ブランドイメージや技術の融合によって生まれた新たな魅力と、成功のポイントをご紹介します。
事例1.よーじや×カクダイ製菓
- 老若男女に愛される「クッピーラムネ」とのコラボで新たな見込み層へのアプローチ
- コラボ商品の数量限定販売による希少価値の訴求
- 半世紀以上の歴史を持つ老舗同士による親和性・信頼性の高い企画の展開
参考:京都発ブランド、よーじや×ノムラテーラーのコラボ生地が登場!両店舗にて地域住民も参加できるワークショップを開催
同社では、既存顧客以外のファン獲得を目的に、コラボ事業を展開。よーじやグループの広報を担う出野さんは「若年層に人気の高い企業さまとコラボしたことで、新たな層へアプローチできていると感じられて嬉しい」と下記のインタビュー記事でコメントしています。
事例2.FERNANDA JAPAN×山梨県モリタファーム
- サスティナブルな取り組みとしての公益性の訴求
- コラボの経緯や思い、周囲からの反応を当事者の言葉で伝えることでのブランドイメージ向上
- 毎年実施する中での「今年のこだわり」による継続性と新鮮さを両立
参考:大人気の「モモコレクション」が今年も登場。魅力を引き出してくれる”もぎたて桃“の香り
事例3.コーセー×フランク ミュラーウォッチランドグループ
- 世界的高級機械式時計ブランドとのコラボによる話題性の創出
- 相手先ブランドの魅力を通して自社技術力や挑戦姿勢などの発信
- 双方のブランドテーマ「美と時」による親和性の強調
参考:TIME&BEAUTY 1秒1秒が、あなたの輝きになる。『コスメデコルテ』のリポソーム美容液が、スイスの高級機械式腕時計ブランド『フランク ミュラー』とコラボ 6月1日(日)より数量限定販売
食品・飲料業界の企業コラボの事例5選
競合の多い食品・飲料業界においては、時代のニーズに応じた差別化が不可欠です。企業コラボによってどのように付加価値が生まれているのか、5つの事例をもとにご紹介します。

事例1.老祥記×フジッコ
- 「神戸の食文化の向上」という地域性と社会性を意識したコンセプトを展開
- 神戸市内の企業や学校に限定した地域内連携による価値創出
- 体験イベントの実施による双方向コミュニケーションを向上
参考:【神戸市】元祖豚饅頭 老祥記と、フジッコがコラボ!レシピは神戸国際調理製菓専門学校が開発!〜豚饅 × 食品メーカー × 学生と、異なる3ジャンルによる、夢の共演
事例2.dely×マルコメ×RIZAP
- 共通のゴールに向けた3社連携による多角的なアプローチ
- Z世代に人気のインフルエンサーによる情報格差の仕掛け
参考:国内No.1のレシピプラットフォーム「クラシル」、マルコメ「ダイズラボ 大豆のお肉」、RIZAPとの3社コラボタイアップでヘルシーライフを応援!
事例3.カネカ食品×東京国立博物館
- 食品企業×国立の博物館という意外性のある異業種コラボ企画
- 記念日に合わせたタイムリーな施策による話題づくり
- 共通テーマの提示による両者の親和性と信頼感の演出
参考:カネカと東京国立博物館のコラボ企画「カネカ×TOHAKU茶館」を開催
事例4.にんべん×斎藤麩屋
- コラボ商品の販売に加えた店頭でのレシピ配布や情報提供
- メニュー開発担当者のコメント掲載による共感喚起
参考:鰹節専門店にんべん×斎藤麩屋 かつお節を通じて楽しむ日本の伝統食材「麩」コラボ企画 2025年6月1日よりコラボメニュー期間限定新発売!
事例5.パンチョ×ファミリーマート
- 実店舗がない地域の顧客への認知拡大と新規層の獲得
- 第8弾となる継続的な企画にもみられる新規性と話題性の維持
参考:ファミマとパンチョのコラボ史上最大、麺量400gの特盛ナポリタンが爆誕!パンチョ監修「特盛 太麺!チーズナポリタン」がファミリーマートより6月24日(火)に発売
メーカーの企業コラボの事例3選
変化の激しい市場に対応するため、メーカーには常に新たな技術や手法を学び、柔軟に取り入れられることが求められます。他企業との技術連携によって新たな価値を創出した3つの事例をご紹介します。
事例1.ニッコー×小松マテーレ
- 思いを共有する異業種同士の連携による新たな注目の喚起
- 石川県内企業同士による地域性とサステナビリティを掛け合わせた商品開発
- 素材と用途の垣根を超えた環境配慮型のものづくりによる社会性の訴求
参考:ニッコー×小松マテーレ「紙コップを、捨てない器へ。」石川県発、サステナブルな異業種コラボ商品が誕生
事例2.ベンキュージャパン×エコーネス
- 両社の技術力を融合させた没入感ある体験価値の提供
- 「自分時間」をテーマに、未認知層へのアプローチを実現
- 使用シーンに基づく製品提案による新たな価値の創出
参考:BenQがノルウェーの家具メーカー エコーネスと初コラボ。”自分時間”を、極上の体験に ストレスレス®のショールームにてBenQの天井モバイルプロジェクター『 GV50 』を展開
事例3.パナソニックグループ×川上産業
- 「環境に配慮」を軸とした共通の価値観による協働企画の展開
- 地域イベントとの連動により社会的なメッセージの発言を強化
- 参加型ワークショップによる製品理解と共感の醸成
参考:パナソニックとプチプチメーカーの川上産業が初めてのコラボ、山形県朝日町の「空気まつり」でワークショップを実施
スポーツの企業コラボの事例3選
スポーツは、年齢・性別・国籍を超えて人々の心を動かすコンテンツです。熱量の高いファン層とのつながりを活かし、ブランドや製品の新たな魅力を引き出す3つのコラボ事例をご紹介します。
事例1.DONGRAMYPROJECT×オリックス・バファローズ
- SNS連動のフォトキャンペーンによる話題性と拡散力の創出
- 野球観戦の思い出化と商品体験を結びつけたエンタメ型プロモーションの展開
- 購入特典として選手関連イベントの抽選企画を実施し、潜在層の獲得を促進
参考:【あの大阪の熱い球団オリックス・バファローズとの限定コラボ】バファローズ×人生4カットフレームが期間限定発売開始!!コラボ商品やスペシャルなイベントも見逃せない!
事例2.タカヤマ×ヴィアマテラス宮崎
- 地元サッカーチームと連携した暑さ対策商品の共同開発
- 収益の一部をチーム運営に還元する社会貢献型モデルの実績
- 地域に根ざした企業とクラブのコラボによる地元への訴求力を強化
参考:【宮崎県】タカヤマとヴィアマテラス宮崎のコラボ商品が登場
事例3.アシックスジャパン×A.P.C.
- 日本の伝統技法とA.P.C.のデザイン哲学を掛け合わせた商品開発
- アスリート着用による機能性とデザイン性の信頼向上
- スポーツ×ファッションのクロスオーバーによる新市場への展開
参考:アシックスとA.P.C.がアパレルとシューズを揃えたテニスコレクションを発売
クリエイティブ・アミューズメントの企業コラボの事例3選
感性や体験を重視するこの業界では、ユーザーの心を動かす演出が広報PRのカギとなります。共感や驚きを生み出した、コラボ事例を3つご紹介します。

事例1.ベスト-アニバーサリー×コニカミノルタプラネタリウム株式会社
- 和の要素を取り入れた「ここでしかできない」独自性のある世界観を演出
- 先着20組限定で人気商品をプレゼントし、特別感と希少性を訴求
参考:「和婚スタイル」×「コニカミノルタプラネタリアTOKYO」ウエディングフォトコラボ星の輝きを詰め込んだドリンク&バスソルトをプレゼント
事例2.新江ノ島水族館×横浜市交通局
- 企画展示のテーマと連動したイベントにより、参加ハードルを下げ、幅広い層にアプローチ
- 利用者の多いアプリを活用した、参加ハードルの低減と潜在層の獲得
参考:【3月7日調査開始】水族館と地下鉄がコラボ!謎解きイベント「潜水列車ディープブルー号のナゾトキ調査」を開催
事例3.ヘラルボニー×ダイキン工業
- 芸術と空調技術の融合によって、空間演出としてのエアコンという新たな価値を創出
- 既存イメージにとらわれない提案で生活者の感性に訴求
参考:ヘラルボニー、”エアコンが空間を彩るアートになる” ダイキンの新ブランド『The Art Line』で期間限定コラボを展開
観光宿泊の企業コラボの事例3選
最後に、観光宿泊に関する企業コラボの事例を3つご紹介します。いずれも、地域性やトレンドなど、観光ならではの特性を活かした企画ばかりです。観光業界においてのコラボ企画のヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
事例1.びわ湖大津プリンスホテル×琵琶湖博物館
- 子どもの自由研究にも活用できる具体的な利用シーンを提案
- 地域経済の発展と観光促進への貢献という地域性にもアプローチ
参考:【びわ湖大津プリンスホテル】琵琶湖博物館とコラボレーション 寝ても覚めてもびわ湖の魅力に浸れる 泊まって学ぼう!びわ湖体験ルーム
事例2.ハイアット セントリック 銀座 東京×すみだ水族館
- 互いのサービス利用を促進するコラボ企画を展開
- 季節感を活かした清涼感のあるビジュアルによる注目度の向上
参考:ペンギンやチンアナゴなど、すみだ水族館の人気者がスイーツに!昨年大好評のコラボレーションアフタヌーンティーが2025年バージョンとして今年も登場「すみだ水族館コラボアフタヌーンティー2025」
事例3.三井不動産ホテルマネジメント×くまモン
- 好評を得たコラボ客室を増設と、対象ユーザー層の拡大による刷新
- コラボ客室の利用シーンの明確化による潜在層への訴求
参考:くまモンと過ごす特別な旅!人気の「くまRoom®」が熊本の魅力を詰め込みリニューアル!新たな客室タイプと客室数を増やし、さらにバージョンアップ!
双方の強みを融合し、独自の広報PR施策を
本記事では、異なる視点や価値観を持つ企業がコラボをすることで、新規顧客層へのアプローチやブランドの価値向上などのメリットを得られることをお伝えしました。今回ご紹介した事例を、自社の業界やコラボを検討している企業の参考として活用し、目的の共有や関係者との連携、共感を呼ぶストーリーの設計に、ぜひ取り組んでみてください。
双方の強みを活かし合いながら、共通のゴールに向けて歩むパートナーとの共創が、これまでにない広報PRの成果につながるはずです。
PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。
PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をするこのシリーズの記事
- あわせて読みたい記事テレビCM・テレビ広告の基礎知識|効果と注意点、制作費、成功事例を紹介

- 次に読みたい記事広報研修の始め方とは?社内で広報PR人材を育成する体制と5つの実践ポイントを解説

- まだ読んでいない方は、こちらから【2020年2月版】広報PRトレンドウォッチ!コロナウイルスの時事情報はどう扱う?

- このシリーズの記事一覧へ

